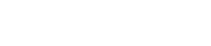トラウマをめぐる10の神話―最新研究から解き明かす性格特性・レジリエンス・治療―
ジョエル・パリスによる『トラウマをめぐる10の神話――最新研究から解き明かす性格特性・レジリエンス・治療』(黒田章史・市毛裕子共訳、誠信書房)を翻訳出版することになった。
本書のタイトルに「神話」という言葉が掲げられていることから、一見、扇情的な内容を想像される方もいるかも知れない。
しかし、実際にはその正反対であり、トラウマに関する多くの通説を、科学的エビデンスに基づいて冷静に見直そうとする誠実な書物である。
パリスは、政治的・感情的なバイアスから距離を取り、精神医学や心理学の知見をもとに、トラウマとパーソナリティの関係を明快に描き出している。
とりわけ、「トラウマを経験したからといって必ずしも有害な結果がもたらされるとは限らない」「人間のレジリエンス(回復力)は過小評価されている」といった指摘は、臨床に携わる専門家だけでなく、広く一般の読者にとっても大きな示唆を与えるものだろう。
その一方で、本書の内容は、現在の「トラウマをめぐる言説」の中で当然とされている価値観や利害と鋭く対立する部分を含む。
パリス自身も、「(本書のような立場は)敵対的な反応を招くことを覚悟する必要がある」と語っており、原著の出版にあたっては、ある種の覚悟が必要だったことは間違いない。
実際、今回翻訳出版を進める中でも、編集担当者から「あとがきで自分の名前を出さないで欲しい」という要望を受けた。
(「訳者あとがき」の中で、しごく普通の編集担当者に対する謝辞だったものが、何やらものものしい誠信書房に対する謝辞に置き換わっているのはその要望に応じた結果である)。
科学的根拠に基づく、ある意味ではごく中立的な立場の書物であるにもかかわらず、編集者としてそれに関わったことが他の仕事に影響しかねないという現実には、少なからず驚かされた。
現代社会では「多様性」や「寛容」がしばしば(表向きは)標榜されるが、実際には一定の言説や感情的圧力によって、異なる視点が排除されがちであるという嘆かわしい風潮がある。
本書が、トラウマに苦しむ人たちへの新たな理解の扉を開くだけでなく、異なる視点を排除するような硬直した言説や思考に対して、健全な問い直しを促す契機となることを願っている。
訳者あとがき
あなたが、専門家か、患者か、あるいはその家族であるかは問わない。まずは、以下の面接における治療者と患者のやり取りをご覧になっていただきたい。
患者:(前略)……8歳の時に性被害にあったことが私の病気の原因だと思わないなんて、信じられない。だってそうでしょう?私は心的外傷後ストレス症(PTSD)と診断されたし、あれは私の人生に起こった本当に大きな出来事だったのに。
治療者:あなたの人生の中でも、大きな出来事に違いなかったと思いますよ。大したことではないなんて、思いたくもありません。でも性被害にあった子どもの中には、後遺症が全く現われない子もいれば、長期にわたり、より深刻な影響を受ける子もいるのです。深刻な影響が長く続く子どもたちは、もともと過敏で(患者は静かに泣き始める)家族の中でも孤立していて、心の支えを求めて両親に話しかけることが出来ないところが違うのです。間違いなくあなたは後者だと思います…(中略)。
あなたは恐らくとても敏感な子どもで、性被害にあったことから、他の子どもよりも大きな影響を受けたのでしょう。だからといって、加害者が罪を犯していないということには少しもなりません。しかし不運な出来事を、他の人よりも、より外傷的にさせるような何かを、あなたが生まれつき持っているということもわかるのです。どうでしょう、これは理解できますか?
患者:(頷く)すごく悲しいです…‥。
治療者:そうですよね…‥‥‥脳は小さい時に形作られるものですから。境界性パーソナリティ症を発症する人の脳では、感情のコントロールがうまく出来ず、さらに前頭葉の理性的な働きがそれを十分に抑えることができないため、最終的にはその感情の反応パターンが脳の神経回路に深く刻み込まれてしまうのです。
このやり取りの中の治療者の説明を読んで「しごく当たり前の内容だと思うが、これが何か?」と思う人がいたなら、その人は必ずしも本書を紐解く必要はないかもしれない。だが、そのような感想を抱く人は、残念ながらとても少ないだろう。呆気に取られたり、場合によっては「傷ついている人に対してこんな対応をするのは許し難い暴挙である」と考えて怒り出したりする人の方がずっと多いのではないか。
だがこれは実は境界性パーソナリティ症(BPD)を独自の精神症候群として特定し、BPDの「父」と呼ばれるJ.G.ガンダーソンが、この疾患の治療者の教育研修用に作った摸擬面接ビデオの一節なのである(この面接の全文が知りたい方は、「JG.ガンダーソン:境界性パーソナリティ障害治療ハンドブックー「有害な治療」に陥らないための技術ー、黒田章史訳、岩崎学術出版、2018」の中に収められているので参照されたい)。つまりガンダーソンは、PTSDに罹患している患者に対して、治療者がこのように対応するのが望ましいと考えていたのである。PTSDという同じ疾患に対して取るべき対応に関する、前者と後者の間にある認識の隔たりは、天を仰ぎたくなるほどに大きい。本書は後者に属する多くの(専門家を含む)人々が共通に抱いている誤解―「神話」―を払拭するために書かれた書物である。
トラウマーとりわけ幼少期の逆境―が、その後の人生においてさまざまな精神的問題の原因となるという考えは、現代社会において広く受け入れられている。トラウマ的な出来事自体は紛れもない現実であり、それが深い苦痛や深刻な精神病理を引き起こす可能性があることも否定し難い。しかし、本書が終始問いかけるのは、「同じようにトラウマを経験しても、何らかの障害を発症する人もいれば、そうでない人もいるのはなぜか?」という根本的な疑問である。そして著者であるパリスは、その答えを「トラウマ経験だけでは、病的な反応の発生や経過を予測できない」という知見から導き出し、トラウマやPTSDに対する我々の認識を基本的に見直すよう促している。
例えばPTSDの診断基準を満たすようなトラウマ的出来事に曝露された人々のうち、実際にPTSDを発症するのは極めて少数であるというのは、実は良く知られた事実である。一般人口において、重大なトラウマとなるような出来事を生涯で経験する者の割合は75%以上にも達するが、トラウマに曝された人々の90%は障害を発症しない。これは、トラウマがPTSDの発症にとって必要条件ではあっても、決して十分条件とは言えないことを明確に示している。その理由は、PTSDが単一の原因によって引き起こされるような疾患ではなく、他の多くの精神疾患と同様に、生物心理社会的な起源を持つ複雑な症候群であるためである。すなわち、個人の遺伝的な脆弱性(とりわけ神経症傾向のようなパーソナリティ特性の程度)、過去のトラウマ経験や複数の逆境の累積効果、そして社会的支援の有無といった様々な要因が複雑に絡み合い、トラウマ体験に対する個人の反応を調整しているのである。トラウマは、PTSDを含む広範な精神病理に対する非特異的なリスク要因の一つに過ぎず、それ自体で転帰の大部分を説明するものではないという知見の重要性は、本書全体を通じて繰り返し強調されている。
こうしたトラウマに関する誤解―神話―がもたらした、とりわけおぞましい出来事の一つが、1990年代に米国で猛威を振るった「回復記憶運動」である。この運動を主導したジュディス・ハーマンらの主張は、幼少期のトラウマ記憶はあまりに苦痛であるため意識から「抑圧」され、その後、特に治療の過程で「回復」されることがある、というものであった。しかしトラウマ体験を経験した人々が、それを忘れようと懸命に努めることこそあれ、「抑圧」というメカニズムによって記憶が丸ごと意識の外に追いやられるというエビデンスは存在しない。むしろPTSDの中心的な症状の一つは、トラウマ的な侵入記憶の存在、すなわち過剰な記憶なのである。また、治療によって「回復」したとされる記憶の多くが、治療者の示唆や暗示、患者の想像力によって作り上げられた虚偽記憶であることが、数々の研究や実際の裁判事例によって明らかにされている。この回復記憶運動は、無実の人々への誤った告発、家族関係の破壊、そして不適切な治療がなされる原因となるなど、臨床現場に計り知れない悪影響をもたらした。
こうした過去の痛ましい経験を踏まえ、本書は一般の臨床家が、トラウマやPTSDに対する認識を、個人的な信念や感情ではなく、適切な科学的知見に基づいて改めることの重要性を訴えかける。例えば臨床家は、患者の語る劇的なトラウマ体験に強く心を動かされ、何らかのリスク要因が精神障害の原因と言えるかどうかに関して、不適切な結論を下してしまう可能性がある(相関関係と因果関係の混同)。また、劇的な逆境のように目につきやすいものは、過度に重視される傾向があることを意味する「利用可能性バイアス」や、特定のリスク要因が重要であると事前に臨床家が確信していることにより生じる「確証バイアス」も、臨床を行う際に警戒すべき代表的なバイアスである。残念ながら臨床家の多くは、そのようなバイアスを回避するための訓練を受けていない。
トラウマに関する誤解―神話―は、精神療法のアプローチにも影響を与えている。PTSDに対して、これまで暴露療法やEMDR等の「トラウマに焦点化した」治療法が推奨されてきた。トラウマ体験に由来する症状に対して、記憶の処理を重視する治療をおこなうのは一見合理的に思えるが、これらは標準的な認知行動療法と比べて特別に優れた効果を示すわけではない。また、トラウマの記憶や体験の語りに過度に重点を置く治療は、必ずしも患者の利益になるとは限らない。むしろそうしたアプローチは、患者の自信や主体性を育むどころか、かえって被害者意識を強めてしまう恐れがある。本書は、PTSD治療において重要なのは、患者が「犠牲者(victim)」ではなく「生き延びた者(survivor)」として自分自身を捉え直し、人生の主体性を取り戻すことへの支援であると繰り返し強調している。
以上のような立場から、パリスは、PTSDの治療では過去のトラウマのみに注目するのではなく、むしろ患者のレジリエンス(回復力)を高めることに注力すべきだと主張する。なぜなら、レジリエンスの重要な要素である「社会的支援ネットワーク」の構築や、PTSDのリスクと関係の深い「神経症傾向の高さ」により生じる問題を緩和する上で、治療者は大きな役割を果たすことが出来るためである。たとえば神経症傾向は遺伝的な影響の下に形成されるが、こうした特性が引き起こす問題に対しても、治療者は適応に役立つ技能を教えることにより支援できる――本書のこのようなメッセージは、治療者だけでなく、患者やその家族にとっても大きな希望となるだろう。その意味で本書は、単に従来のトラウマ理論を批判するだけでなく、困難な状況に置かれた人々が適応し、回復していくプロセスに焦点を当てた、「レジリエンスという希望」についての書物と言える。
本書 Myths of Trauma: Why Adversity Does Not Necessarily Make Us Sick の著者であるジョエル・パリスについて簡単に紹介しておこう。パーソナリティ症研究学会(ARPD)の前会長、カナダ精神医学誌の元編集長を務めた経験を持つパリスは、マギル大学精神科学部長を経て、現在は同大学の名誉教授である。境界性パーソナリティ症(BPD)に関する世界的権威として知られるほか、精神疾患における過剰診断、神経科学と精神療法の関係、精神疾患における遺伝と環境の相互作用など、幅広いテーマで多数の著作がある。
本書の翻訳は、黒田が序章~第4章を、市毛が第5~9章を担当し、それぞれの訳稿を相互に校閲することで、訳語と文体の統一を図った。また市毛は、本書について「従来のトラウマ理論への批判というより、レジリエンスという希望についての書物ではないか」という本質的な感想を寄せてくれた。この言葉は、本書を訳出する上で終始、導きの糸となっていたことを付言しておきたい。
著者のパリスも述べているように、トラウマはしばしば政治的な問題となっており、PTSDに対する現在の診断や診療の在り方に異議を唱える本書のような書物は、それがいかに科学的エビデンスに基づいていたとしても敵対的な反応を覚悟しなければならない。勇気を持って本書を出版してくれた誠信書房に感謝する。
2025年6月 黒田章史