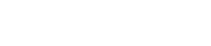「隠れBPD」という問題ーその3ー
ツィマーマンがおこなった研究とは、アメリカのロードアイランド病院を受診した3674名の外来患者のうち、BPD(境界性パーソナリティ障害)という診断が下された390名の患者を対象として、自傷行為や自殺行動を取った患者と取らなかった患者群を、人口統計学的および臨床的特徴に関して比較したものである。
自殺傾向/自傷行為に関する診断項目の評価がなされなかった1名を除いた389名の内訳は、男性が110名(28.3%)、女性が279名(71.7%)で、これはこれまでに明らかになっている、外来受診するBPD患者の男女比に概ね等しい。
この研究の主題となっている、自殺傾向/自傷行為という診断項目を満たしていたのは210名(54.0%)で、前回にも述べたようにーそしてこの疾患の公的イメージとは裏腹にーBPD患者全体の半数強に過ぎなかった。
では、自殺傾向/自傷行為という診断項目を満たしていたBPD患者のグループと、満たしてなかったグループは、どのような点が、どれくらい異なっていたのだろうか。
まずは異なっていた点から。
双方の患者グループの内、自殺傾向/自傷行為という診断項目を満たしたグループの方が、満たさなかったグループよりも、自殺念慮をより多く報告し、入院経験もより多い傾向があった。
もっとも自殺傾向/自傷行為がみられた患者なら、自殺念慮を訴えたり、入院したりする頻度が多いのも当然だから、これは想定範囲内の結果と言える。
そして少々意外なことに、双方のグループが異なっていたのは、ほとんどこの項目だけだったのである。
たとえば双方のグループでは、抑うつ症状、不安症状、さらに怒りの程度といった症状に関して差はみられなかった。
(ちなみにBPDと併存している、うつ病などの精神疾患の数に関しても、両群の間にはほとんど差はみられなかった)。
それだけではない。
自殺傾向/自傷行為がみられようがみられまいが、青年期においても、成人期以降も、BPD患者の中長期的予後を占う上で最も重要な指標の一つである、心理社会的機能には有意な差が認められなかったのである。
この結果から容易に想像出来ることではあるのだが、患者が長期にわたり失業する可能性や、障害年金を受ける可能性に関しても、自殺傾向/自傷行為のみられた群とみられなかった群の間で差はみられなかった。
さらに、小児期に虐待やネグレクトをされた経験があるかどうかに関しても、自殺傾向/自傷行為があるBPD患者とない患者との間で、有意差はみられなかったのである。
自殺行動や自傷行為は、確かに目立ちやすい症状ではある。
だが、当然のことながら、BPD患者は腕を切っているから悩んでいるわけではない。
むしろ順番は逆であり、彼らは心理社会的能力に乏しく、社会生活が上手くいかないから腕を切ったり、自殺企図をおこなったりしているのである。
ただし、もちろん社会生活が上手くいかない患者の全てがそうした行動に出るわけではない。
だから半数近くのBPD患者が自殺傾向/自傷行為を示さず、しかも著しい苦悩に苛まれているというのは少しも矛盾した事ではないのである。
BPD患者を適切に治療するためには、自殺傾向/自傷行為といった「派手な」症状にばかり目を向けるのではなく、その基盤にある心理社会的能力の不全という問題に目を向け、対処していく必要がある。
この研究は図らずもそれを裏書きしてくれたという意味で重要なものと言えるだろう。