「境界性パーソナリティ障害治療ハンドブック ー<有害な治療>に陥らないための技術ー(J.G. ガンダーソン著、黒田章史訳、岩崎学術出版)」
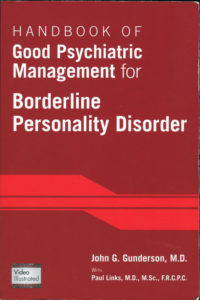

■訳者あとがき
あなたが医療あるいは臨床心理に携わる専門職であるか、この疾患に悩んでいるご当人
であるか、ご家族であるかはひとまず問わないことにしよう。本書を手に取ったからに
は、あなたは境界性パーソナリティ障害(BPD)に多少なりとも興味を持っているはずで
ある。J.G.ガンダーソンによって著(あらわ)された本書は、そのような人たちのいずれ
に対しても、必要最小限の正確な知識を提供するためのものである。
必要最小限の知識なんて、わざわざ本書など読まなくても、今どきネットやメディア
を通していくらでも身につけられると思う人もいるかもしれない。そう思う人はこれか
らBPDの基礎知識に関していくつか問題を出すので、どれほど答えられるか試しに解い
てみてほしい。採点は1=正しい、2=間違いではないが、適切とは言えない、3=間違
っているだけでなく、有害ですらある、という形でつけてもらおう。
【問】BPDの病因とその経過に関して、あなたは以下のように考えるべきである。
A.BPDの病因は、非常に過酷な家庭環境や愛情不足な状況で育ったことである。
B.BPDのもう一つの病因は、一見すると恵まれた家庭環境に育ったように見えても、
その家の「こうでなければならない」という基準に支配されて育ってきたことであ
る。
C.BPDの症状は6年で約半数が寛解する(診断基準を満たさなくなる)。
解説
【問】BPDの原因とその経過に関して、あなたは以下のように考えるべきである。
(第3章「診断の開示」および「どのように診断を開示するか」、さらに第9章ビデオ1
「心理教育」を参照)
A.:3。そうではない。BPDの病因として最も重要なのは遺伝的要因である(~55%)。
それに加えて患者が家庭の内外で、生まれ持った資質に応じて経験する環境要因(家族
に共有されない[ユニークな]環境要因)が重要であり、家族に共有される環境要因が
BPDの発症に対して果たす役割は極めて小さい。本書の中でガンダーソンが、BPDの
心理教育をおこなうに当たって「(BPD患者は)育ててくれる人々に対して極めて過敏
で反発を起こしやすい遺伝的素因を持って生まれてくる」「(BPDを発症しやすい子
どもは)他の子どもに比べて、親の行動が拒絶あるいは怒りに由来するものと受け取り
がち」といった要素を強調して説明しているのはそのためである。
B.:3。そうではない。上記の項目Aに対する解説を参照すること。項目Aの場合と同じ
ように、巷(ちまた)で流布されているこうしたタイプの誤った説明は、BPD患者が「
被害者のポジションを取る(自分は誰かの犠牲者であるから、なすべきことは犯人を告
発することであって、自分自身が変わる必要はない、という問題の多い信念を抱く)」
ことに繋(つな)がりやすいだけでなく、BPD患者の家族に対する不当な偏見を生み出
す原因となるという意味で極めて有害である。
C.:2。BPDの寛解率(診断基準を1年間満たさなかった患者の割合)は、ガンダーソン
らがおこなった長期予後研究(CLPS)によれば2年で約50%、10年目までに85%で
ある。「6年で約半数が寛解」という数値を支持するデータはないが、ザナリーニら
のおこなった長期予後研究(MSAD)によれば、BPD患者の約半数が「持続的寛解(4年間
診断基準を満たさない)」をするに至る期間は約6年である。ただしこの研究で「持続的寛
解」という概念をわざわざ用いているのは、4年もの長期にわたり診断基準を満たしていな
くても、それが「回復」とは異なることを示すためであり、通常BPDの予後を語る場合に
「持続的寛解」の数値が用いられることはない。
さてあなたはどれくらい正答できただろうか。一問も正答出来なかっただけでなく、
解説を読んでも半信半疑という人もいるかも知れない。そういう人がいるのも無理はな
い。この問題は今年(2017年)放映された某「教育番組」において、全て1と採点する
のが正しいと説明されていたのだから。まずはそのような先入見を持っているーあるい
は持たされているー人たちにとって、本書の与える情報は極めて大きな意義を持つこと
になるだろう。
また本書は、上記の問いに比較的簡単に答えられるような人たち(おそらくは治療に携
わる専門家)にとっても、BPD患者と治療的関わりを持つ上での基本に関して重要な示
唆を与えることは間違いない。たとえば本書第9章の模擬面接ビデオで示されている、
患者とセラピストのやり取りを一渉(ひとわた)り眺めてみれば、BPDを治療していく上
で治療者に必要とされる基本的姿勢が、いわゆる「カウンセリング的なるもの」からい
かにかけ離れているかがわかるのではないだろうか。
セラピストは常に治療の主導権を握り、「専門家(知識ある者)」として振る舞い、も
っぱら演繹的(えんえきてき)な姿勢を取るーすなわちBPDに関する一般的な理論に基づ
き、個々の患者にみられる具体的な問題について(「この問題は~という病理に由来す
ると思われる」「これは~という症状に相当する」といった形で)推論し、説明してい
くという姿勢で治療に臨む。また患者を決して「お客様扱い」することなく、治療にお
いて患者が積極的な役割を果たすよう粘り強く求めていく(患者は変わらなければならな
い!)。また治療外で患者が充実した生活を送れるようになることを重要な目標として
定め、なるべく早く学校、仕事、あるいは家事労働に就くよう指導していく。
治療に携わる専門家の中には、BPDという疾患で苦しんでいる患者に対して追い打ち
をかけるような介入であるとして、本書で示されているようなセラピストの姿勢に対し
て強い違和感―ことによると嫌悪感―を抱く人もいるかもしれない。だが精神科以外の
領域の治療に目を向けるなら、こうした治療者の姿勢はごく一般的かつ常識的なものに
過ぎない。また患者が直面するさまざまな問題は不可解なものではなく、筋道立てて理
解すること、さらに変えていくことさえ可能なものであることを、患者や家族に対して
折々(おりおり)伝えていくのは、この疾患の治療を行なうにあたって欠かすことのでき
ない手続きなのである。このような方向づけがなされない限り、患者が自分を変え、「
きちんと生きて(get a life)」いくという、短期的には苦痛を伴う作業に責任を持って
継続的に取り組み、それを家族が支えていくというプロセスを、首尾よく進めていくこ
とは難しいだろう。
またこうした姿勢は、本書の中でセラピストが「無知の姿勢(not knowing)」を取る
ことの重要性を強調しているのと矛盾すると思う人だっているかもしれない。だが著者
も述べているように「専門家(知識ある者)の姿勢」と「無知の姿勢」は決して両立し得
ないわけではない。むしろ知り得る知識はできる限り得ようと努力した上で、得られた
知識について必要とあらばどこまでも再検討していくという姿勢を取ることは、治療者
だけでなく患者にとっても極めて大きな意義を持つのであるーいやむしろ患者にとって
こそより重要な意義を持つと言うべきか。
もちろん訳者は上記のビデオで示されている面接の進め方について、必ずしも全面的
に賛同するわけではない。BPD患者に対して治療的介入をおこなう場合、どのような内
容の介入をおこなうかということと同程度あるいはそれ以上に、どのような形で介入を
おこなうかが重要であるが、この模擬面接ビデオでは「どのような形で」という点に関
する配慮がやや不充分な箇所が散見されるように思われるためである(それが具体的に
どのような箇所を指しているかについては、本書第9章末の「訳者コメント」を参照さ
れたい)。
しかし本書で示されているような方向性が、BPDに対する関わり方の基本として治療
者の間で共有されるなら、この疾患に対する治療が大きく底上げされていくことは間違
いない。その意味でBPDの治療に携わる臨床家が、「程(ほど)よい(good enough)」
技量を身につけるために最低限必要な知識を提供するという著者の目論見(もくろみ)は
、見事に達成されていると言って良いだろう。また患者や家族が本書に触れ、BPDに関
する正確な知識を獲得し、治療ではどのようなことがおこなわれ、自分たちには何が要
求されるかについて、あらかじめ見当がつけられるようにしておくことは、この疾患の
治療を円滑に進めていく上で大きな力になるに違いない。
ただしBPD治療の底上げを図るという著者の狙いは充分に達成されているとしても、
この疾患を治療していく上で最大の問題と言って良い、心理社会的機能の不全に対応す
るための方法を提示することには、本書においてもやはり成功しているとは言い難いよ
うに思われる(これは著者が、家族を治療資源として活用する方法を、充分に構築でき
なかったこととも関係しているかもしれない)。もっとも、これは決して著者だけの問
題ではなく、弁証法的行動療法やメンタライゼーションに基づく治療といった、これま
でに提唱された主だった治療法においても、ほぼ手つかずのままになっている領域なの
だが。
心理社会的機能の不全に対してどのような治療的対応をおこなうことが可能であり、
そしてそれを実践する上で家族をはじめとした、患者の周囲の人々がいかに重要な役割
を果たすかについて詳細に論じた書物としては、現在でも拙著『治療者と家族のための
境界性パーソナリティ障害治療ガイド』(岩崎学術出版、2014)が唯一のものである。
BPDが回復していく上で、家族を中心とした支援ネットワークが果たす役割の重要性は
、欧米においてもようやく認識され始めたテーマでもあるから、興味のある方は一読し
ていただければと思う。
最後になったが、本書の著者であるJ.G.ガンダーソンについてほんの少しだけ紹介し
ておく。ハーバード大学医学大学院の教授であり、マクリーン病院のパーソナリティな
らびに 心理社会研究部門の責任者でもあるガンダーソンは、BPDに関する世界的権威
の1人というより、この疾患の概念を構築する上で大きな役割を果たした人物として名
高い。また前著『境界性パーソナリティ障害 クリニカル・ガイド』(黒田章史訳、金
剛出版、2006)は既に古典としての地位を確立しているから、本書を読んで興味を持た
れた方は(少々歯ごたえがあることは覚悟の上で)読み進まれると良いかも知れない。
本書を訳出する上で、クリルモッド・トーキョーの三輪知子氏には特別にお世話にな
った。本書に付属している面接ビデオを、第9章に収められているような形へと訳出し
てくれたのである。文体を統一する上で、私自身も文章を多少いじってはいるが、三輪
氏の助力がなければ本書にビデオ面接の内容を収めることができなかったことは間違い
ない。厚く御礼申し上げたい。
また岩崎学術出版編集部の小寺美都子さんには、いつものようにーいやいつもにも増
して!ーお世話になった。正確な訳文を目指すのは訳者として当然の責務だろうが、そ
れを意味の通りやすい日本語になるまで練り直すという作業を、小寺さんは驚くべき熱
意で手助けしてくれたのである。小寺さんがやむを得ぬ事情から、途中で本書の担当を
離れることになったのは残念至極であったが、その代役は長谷川純氏が立派に果たして
くれた。両氏に心から感謝する。
本書を通して、憂慮しなければならないほどに立ち後れた水準にあるわが国のBPD臨
床が、わずかなりとも底上げされることを願ってやまない。
2017年12月
黒田章史
