「境界性パーソナリティ障害の治療ーエビデンスに 基づく治療指針ー(J・パリス著、黒田章史訳、金剛 出版)」
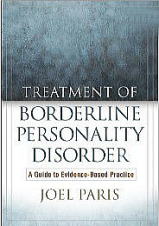
■訳者あとがき
「Get a life」という言い回しがある。取るに足らぬこと、見込みのないことに多くの時間を費やしている人物に対して、それまでのやり方を見直すように促す慣用句である。本書の第9章に登場するこの言葉は、ある意味で本書のキーワードと言って良いかも知れない。最近得られた実証的データに基づき、BPD患者の治療に携わる専門家に対して、家族に対して、そして何よりもBPD患者自身に対して、本書の著者であるパリスは、以下のような形で「Get a life」と繰り返し呼びかけているのだから。
まずパリスはBPDを他の何らかの障害(の異型)とみなし、この診断をつけることを回避するのを止めるよう専門家に対して呼びかける。BPDを無視したところで、こうした患者が抱える症状や問題が消えてなくなってくれるわけではないし、仮に大うつ病や双極性障害などと診断して薬物療法を試みたところで、それが十分な効果を示すことはないのだから。それどころかBPDという診断を受けない場合、患者は専門的治療を受けるチャンスを失うことになるのである。
次にパリスが専門家に呼びかけるのは、BPDを「性格(パーソナリティ)の障害」とみなすのを止めることである。最近おこなわれた複数のフォローアップ研究は、いずれもBPDが比較的短期間のうちに症状面ではかなり大幅な改善を示すことを明らかにしているのだから。すなわちBPDは「変わることなく長期にわたり続く性格(パーソナリティ)の障害」であるどころか、ごく普通の精神疾患の1つに過ぎないのである。DSM-5で従来のⅠ軸とⅡ軸という問題の多い区分がようやく撤廃されたのも、こうした研究結果を踏まえるなら当然のことと言えよう。
第3にこの障害を引き起こしたのは家族であるとみなし、専門家が家族を敵視するのを差し控えるようパリスは呼びかける。近年得られた行動遺伝学的な知見はこのような見方を支持していないし、重篤な機能不全に陥っている家庭に生まれ育ったBPD患者は、ほんの一部に過ぎないのだから。それどころかパリスは、下坂幸三やガンダーソンと軌を一にするように、家族は治療をおこなう上で重要な協力者であると主張する。
第4にもはやBPDに対する精神療法に、DBT(弁証法的行動療法)やMBT(メンタライゼーションに基づく治療)、TFP(転移焦点化精神療法)といったブランド名など不要であるとパリスは専門家に呼びかける。認知行動療法と呼ばれていようが、精神分析療法とされていようが、実際になされている介入の内容(治療を構造化すること、妥当性を確認[validate]すること、自己観察をするよう患者に促すこと)にさしたる違いはないし、得られる効果―後に述べるように効果の限界―も同じ程度なのだから。
BPDに関する正しい知識を身につけるべきなのは専門家だけではない。家族もそろそろ自分たちを責めるのを止め、BPDに関する正確な知識を身につけたり、患者の病理に適切に対応していくための方法について学んだりした方が良いとパリスは呼びかける。ただし家族の対応法とはいっても、少なくとも欧米において現在推奨されているようなものに関する限り、それらはいずれもBPDにみられる行動の一部に対して中立的な態度で反応することにより、悪い状況をさらに悪化させるのを避けるための方法に過ぎない。それでもほんの少し前まで、この障害を引き起こしたという罪状で、家族が患者(と専門家)から一律に非難されてきたことを考えるなら、BPDの治療をめぐる状況が改善の方向へ向かっていることは間違いないのである。
そして最後にパリスはBPD患者に対して以下のように呼びかける。たとえどれほど過去において逆境に晒(さら)され、辛い思いをしたからといって、過去のことにこだわるのは止めたほうが良い。過去に焦点を合わせるような治療をおこなうセラピストたちが、長年にわたって患者にそうした作業をするよう促してきたのは事実だが、そのような作業をいつまでも続けることの有害さは、今では充分に明らかになって来ているのだから。なぜなら過去の出来事は、患者の置かれた状況の全体像を治療者が見て取る上で役立つことはあっても、患者が病気になった理由を説明するようなものではないからである。
その代わりにパリスは患者に「きちんと生きる(Get a life)」よう勧める。それも患者の気分が楽になった後ではなく、今すぐにである。患者は昼夜逆転した生活を送るべきではないし、一日中ゲームをし続けるべきでもない。自分自身が抱える問題を他人(多くの場合には親)のせいにしてみたところで何の解決にもならないのだ。そうしたやり方に見切りをつけ、何らかの形で仕事に取りかかったり、勉強を始めたりすることが患者にとって何よりも重要であるとパリスは主張する。患者がきちんとした社会的役割を担い、現実に根ざした自尊心を持つことが出来るようになればなるほど回復は早まるのである。逆にセラピストがどれほど共感(empathy)や妥当性の確認(validation)をするよう心がけたところで、それだけでは患者の自尊心が実際に高まることはないのだ。
パリスのこうした「出直せ(Get a life)」という呼びかけに対して、あるいは抵抗感を覚える読者もいるかも知れない。しかし本書を一読すれば明らかなように、一見大胆とも見える著者の主張の多くには、しっかりした実証的裏付けがあるのである。もちろん私はパリスが本書でおこなっている主張の全てに賛同出来るわけではない。とりわけ予後に関する見通しは、今となっては甘きに過ぎるきらいがあるだろう。本書の出版後に公表されたフォローアップ研究は、この障害の症状が高率に寛解し、再発率も低いことを改めて裏付けるものだったが、残念ながらそれは必ずしも彼らの社会的予後が良いことを意味してはいなかったからである。
すなわち良好な心理社会的機能(機能の全体的評定[GAF]尺度70以上)を獲得したBPD患者の割合は、調査開始後10年後でもわずか21%に過ぎず、他のパーソナリティ障害(48%)あるいは大うつ病(61%)に比べてはるかに低かった。また心理社会的機能が改善された場合でも、その改善は概して長続きせず、しばしばかなり大きな変動を示したのである。こうした結果を受けて、ガンダーソンらは「この障害の予後についてこれまで抱かれてきたペシミズムは、心理社会的機能に関しては半ば正当化されるように思われる」と結論づけている(Gunderson JGほか; Ten-Year Course of Borderline Personality Disorder: Psychopathology and Function From the Collaborative Longitudinal Personality Disorders Study. Arch Gen Psychiatry. 2011 August ; 68(8): 827?837)。
またBPD患者はなるべく早く仕事や勉強を始めるべきであるというパリスの主張には私も全く異論はないのだが、本書にはその前提として必要とされる、心理社会的能力を高めるための具体的方法に関する記述がない。具体的方法を提示しないまま、ただ「学校に戻れ」「仕事をしろ」と言われても、困惑してしまう患者が多いのではなかろうか。職場や学校に適応しようとさんざん努力したあげく、うまくいかずに仕事や勉学を諦めてしまう患者が少なくないのが実情なのだから。
もちろんこのような問題はパリスだけが抱えているものではない。むしろ「患者の心理社会的能力を高めるための技法」は、従来のBPD治療においてほぼ完全に欠落してきた領域なのである。だからこそ上記の論文においてガンダーソンらは、弁証法的行動療法(DBT)やメンタライゼーションに基づく治療(MBT)といった、BPDに特異的に対応したものとされる治療でさえ、患者が示す深刻な社会的機能の不全を改善する上で、ほとんど役立っていないという指摘をおこなったのである。その上で今後のBPD治療は、社会的機能の障害に対して本格的に取り組む必要があるという見通しを述べている。
以上のような観点から見た場合、本書の中でパリスが繰り返し推奨しているような、極めて短期間の治療を間欠的におこなうという方法が適切であるかどうかは、やはり疑問であると言うほかはない。当然ながら本書で推奨されているような治療を受けた患者の大半は、良好な心理社会的能力を身につけるのが長期にわたり滞ることになるであろうから。すなわち本書は今後のBPD治療の進むべき方向を適切に示しているという意味で、現時点ー幸か不幸か2008年に原著が刊行されて以降、現在に至るまでBPDの治療に関して本質的な進歩は皆無と言って良いーにおける最良の書物であると同時に、現在のBPD治療が抱える限界を明らかにしている書物とも言えるのである。
当然ながらこのような限界は乗り越えられる必要があるだろう。本書と相前後して岩崎学術出版から刊行される予定の小著「治療者と家族のための境界性パーソナリティ障害治療ガイド」は、BPD患者の心理社会的機能を向上させるという課題に対して正面から取り組む目的で書かれた、おそらくは最初の書物である。もちろん私とパリスの立場は大きく異なるが、パリスが本書で示しているような、今後の治療の進むべき方向性を現実のものとするためにはどのような治療構造や技法が必要とされるかについて詳述した書物とも言えるかも知れない。本書と併せてご一読願えればと思う。
最後に遅ればせではあるが本書Treatment of Borderline Personality Disorder :A Guide to Evidence-Based Practiceの著者であるジョエル・パリスについて紹介しておくことにしよう。パーソナリティ障害研究学会(ARPD)の前会長であるパリスは、現在マギル大学(カナダ)の精神科教授であり、Canadian Journal of Psychiatry誌の編集長を務めている。BPDに関する世界的権威の一人であり、とりわけBPD患者の転帰を27年の長きにわたりレトロスペクティヴな形で追跡した研究は名高い。
巷間(こうかん)には現在数多くのBPDに関する書物が存在している(その中には私自身が訳したガンダーソンの名著「境界性パーソナリティ障害 クリニカルガイド(金剛出版)」も含まれている)。しかし私は本書に出会うまで、BPD患者やその家族が日常的に参照出来るような、それでいて専門家に対しても貴重な知見を提供するような書物が、このような形で存在し得るということを知らなかった(とりわけ本書の第5章は、患者自身が再読三読するに値すると思う)。本書を専門家以外の人々にも、広く推奨する所以(ゆえん)である。
2014年1月
黒田章史
